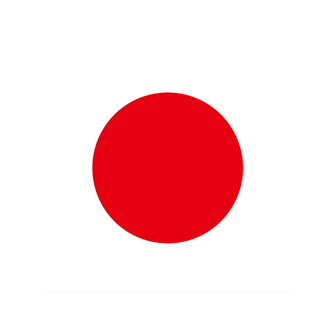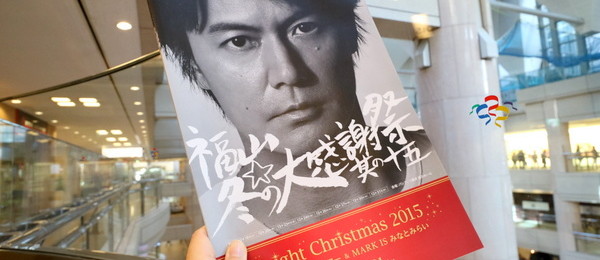祭の撮影をしている時、ひとりの少女と出会った。
私がカメラを向けると、たいがいの子どもはピースをしたり
少なくともにこっと笑って表情がゆるむ。
だが、その少女は表情をくずさず、じっとこちらを見ているだけだった。
はじめは写真を撮られるのが嫌なのかと思ったが、どうもそういう感じではなかった。
少女はいつまでも私の方をじっと見つめ、一度も目をそらさなかった。
カメラを通して少女と無言の会話がはじまった。
私は驚きと尊敬を持って、夢中でシャッターをきった。
ふと突然、あるフレーズがよぎった。
「私が、木を見ているのではない。
木が、私を見ているのだ。」
高校生の時に、出会ったポール・セザンヌの言葉。
当時、この意味がさっぱりわからないでいた。
だが正に今、それが実体験の言葉として置き換わり、
私に迫ってきた。
「私が、少女を撮っているのではない。
少女が、私を撮っているのだ。」
何十年も前に耳にしたセザンヌの言葉が、実体験の言葉に置き換わり
すんなりと自分の中に入ってきた瞬間だった。
絵を描くこと、写真を撮ること。
そこには必ず、被写体が存在する。
それは時に、闘いとも言える「被写体との対峙」であり、
その表現活動は全て、作家の心理作業の連続である。
「被写体としっかり対峙できてるか」
ひとりの少女の瞳は、今後いかなる撮影の場面で
私に問いかけてくるに違いない。